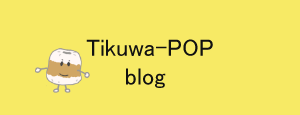素材ダウンロード
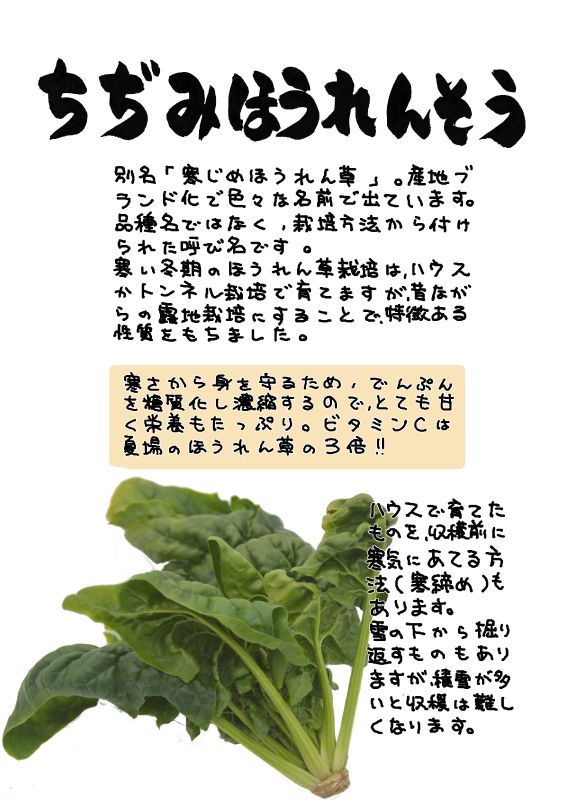
【 寒締め とは? 】
「寒締めホウレンソウ」は、品種ではなく、冬の寒さを活用した栽培技術です。
農研機構 東北農業試験場(現:東北農業研究センター)で開発されました。
昔からホウレンソウや菜っぱ類は、冬に甘くておいしくなることは良く知られていました。雪や寒さに抵抗するためには、凍り付かないよう体内の糖分濃度をあげるという生理的な自己防衛本能を活かし、人工的にその環境をつくってやる、という事で、通常の栽培方法よりも、良食味の野菜を作れることになります。
【 「寒締め」と呼ばれる方法について 】
農研機構の文を一部転載。
https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/043762.html
外気温が5°C程度を割るようになったらハウスの側窓を開放し、冷気にあてます。こうすると、ホウレンソウの場合2週間程度で糖度やビタミン含量が高くなります。また、冷気にさらすと生長が止まるので、長期にわたって出荷できるメリットもあります。
「締めでホウレンソウの硝酸含量が低下」
---「寒締め」でホウレンソウを栽培すると、糖度・ビタミン・食味が向上することを明らかにしてきましたが、このたび、この寒締め栽培で収穫前の気温・地温を低くすると、過剰に摂取すると問題とされる硝酸含量も低下させるのにも有効であることを明らかにしました。
資料では、ハウスの側窓を開放した日以降、どのように変化するかの結果を見ることができます。
要約すると、「糖度が上昇し、硝酸含量は減少した」「シュウ酸含量との相関はなく、変化しない」という内容です。
糖やビタミン含有が高くなる、という点については、有意な効果といえます。
実際に、食べた食味も、貢献していると思われます。
ホウレンソウへ過剰に窒素養分を与えた場合、硝酸含量が増加すると共にシュウ酸含量も増えることが確認されています。窒素は、土の中で硝酸イオンの形で野菜の根から吸収されて運ばれます。窒素が多すぎると、吸収量も増えることになります。
通常食べる量のホウレンソウ程度では、尿結石などのリスクは低いとされています。シュウ酸は水溶性なので、茹でてしまえば30~50%減少するそうです。
御心配な方は、ご参考になさってください。
農水省 食品中の硝酸塩に関する基礎情報
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/syosanen/about/index.html
FAO/WHO合同食品添加物専門家会合は、硝酸塩の摂取と発がんリスクとの間に関連があるという証拠にはならないと言っています。
事あるごとに、このリスク事案はメディア等にちょこちょこ顔を出します。
科学的観点から論じているものを参考にしたいですね。
【 その他 】
外観はしわしわ、ごつごつして、どんなんだろうと思いますが、食べると、とても甘味のある、美味しいほうれん草でした。
調理はとくに、通常と変わりありません。
寒さに強い品種で、縮み系品種が数社からリリースされています。
トキタ種苗 「寒味(かんあじ)」「寒味・極(かんあじきわみ)」
雪印種苗 「雪美菜(ゆきみな)02」
渡辺採種場 「冬霧7」「じっくり朝霧」
廃番があるかもしれません 202401
冒頭で申し上げたとおり、冬の寒さを活用した栽培技術です。
寒さに強ければ、寒締め栽培は可能とされています。
タキイ 弁天丸なども向いています。
発芽適温に注意し、播種時期を探ってください。
寒締め系で、チリチリの縮緬状になった青菜には、雪菜、仙台雪菜もあります。
ホウレンソウはヒユ科で、雪菜はアブラナ科です。
「雪菜」について詳しく解説したリンクはこちら。
https://tikuwapop.com/sozaiDetail.php?num=1459&words=%E4%BB%99%E5%8F%B0%E9%9B%AA%E8%8F%9C
202111改
202201改
202401改