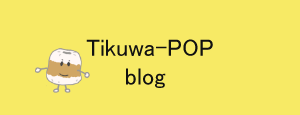素材ダウンロード
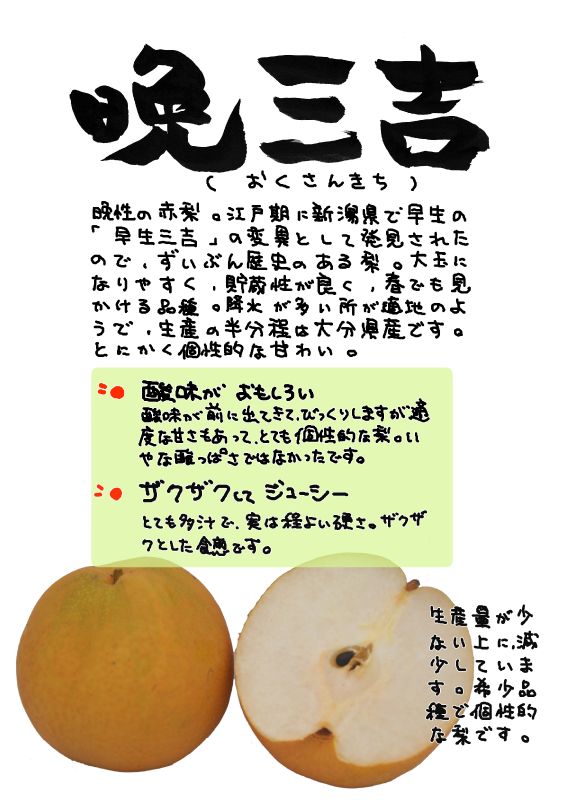
晩三吉 おくさんきち
カテゴリ:くだもの
梨で、酸味を楽しむ という発想は、今では無い不思議体験です。
まずい、という評もありますが、食べてみると クセになるから面白いものです。
ファイル名:20210111.jpg
晩三吉 おくさんきち ばんさんきち
明治時代から栽培されている、とても歴史の長い和梨。
700g程度の、大型になる晩生赤梨です。
大正時代に「長十郎」が一世風靡するまでは、各地で栽培されていたようです。
和梨では珍しい、酸味も楽しむという、不思議な体験ができます。
【 来歴 】
古い品種で、来歴については諸説あります。
江戸時代にも栽培されていたという、「早生三吉」の偶発実生が、新潟県中蒲原郡両川村(現在の新潟市江南区)で発見されたものが、明治になって各地に広まったとされています。
「新雪」「豊月」の親品種でもあります。
晩生(おくて)の三吉なので、略して「晩三吉(おくさんきち)」。
梨のテーマパーク、鳥取二十世紀梨記念館(鳥取県倉吉市)では、過去の歴史を振り返るコーナーがあります。
出荷用のハンコが展示されていて、「晩三吉」もありました。
私も、鳥取の数か所の店舗で、陳列販売されているのを見かけました。
栽培面積は不明ですが、大分、福島 ほか各地で栽培されているようです。
比較的多雨の地域が栽培に向いているそうです。
当方は、石川県で入手。
なお、栽培に関連して、おもしろい資料がありましたので、ご紹介。
「和梨の品種」岩垣駛夫(いわがき はやお) 福島県園芸試験場長
https://www.snowseed.co.jp/wp/wp-content/uploads/grass/grass_195608_02.pdf
雪印種苗さんHPで保存している記事です。
岩垣氏は、りんご育成に従事したほか、日本ブルーベリーの父と呼ばれています。
1956年に書かれたものでしょうか。当時の梨品種を俯瞰して、岩垣氏がコメントを残しています。
当時の梨市場の様子や歴史が記録されています。
「長十郎」「二十世紀」「早生赤」といったところが、当時のメジャーな品種だったそうです。
また、今後期待される品種についても言及されています。
その後の梨品種の趨勢を考えると、とても興味深い内容となっています。
「晩三吉」に関して、「和梨の代表的貯蔵品種」と評しており、当時はメジャーな存在だったことが伺えます。
福島以北では適地といえず、期待した品質におよばないと記されています。
「晩三吉」の交配品種、「新雪」について、試食の機会を得た記述がありますが、1949年発表の品種なので、希少だったのでしょう。
【 食べてみた印象 】
まん丸で、きれいな形の個体。
切ると、とてもジューシーな印象。
食べてもジューシーさはたっぷり感じられました。
甘味はありますが、おとなしい印象。
予備知識なしで食べたので、酸味に驚きました。
最初は、違和感を感じたのですが、だんだんクセになって、とりこになるから不思議です。
おどろくべき 個性的な梨。
梨で、酸味を楽しむ という発想は、今では無い不思議体験です。
時代に合わない部分もあるので、いつまで栽培され続けるのか気になるところです。
酸味という個性も、突き抜けた個性となって、心に残る品種となるでしょう。